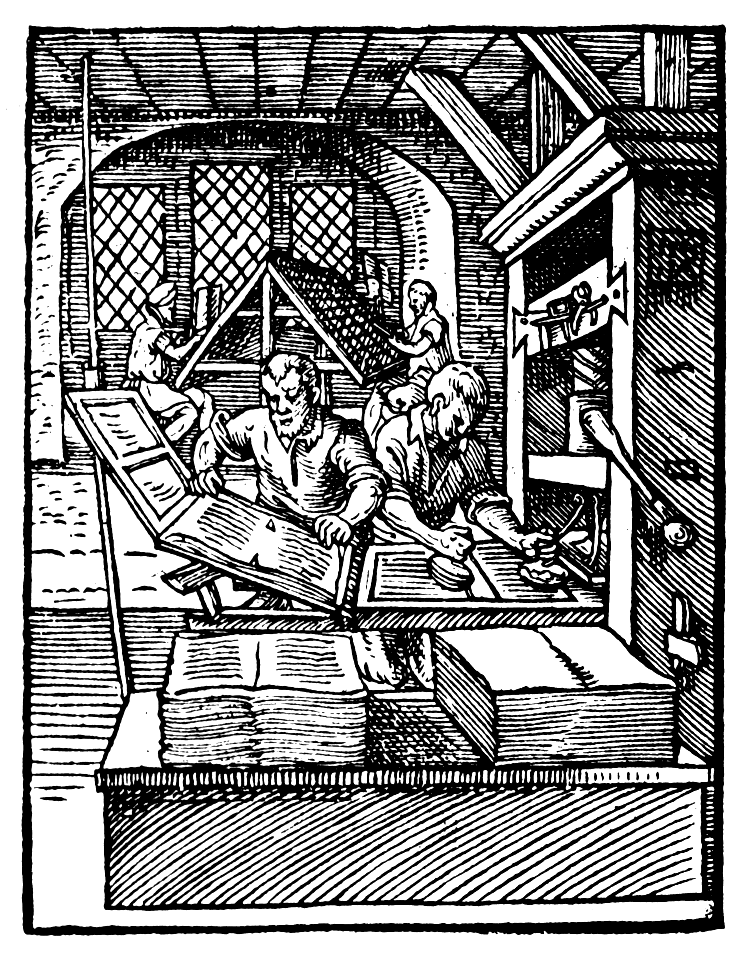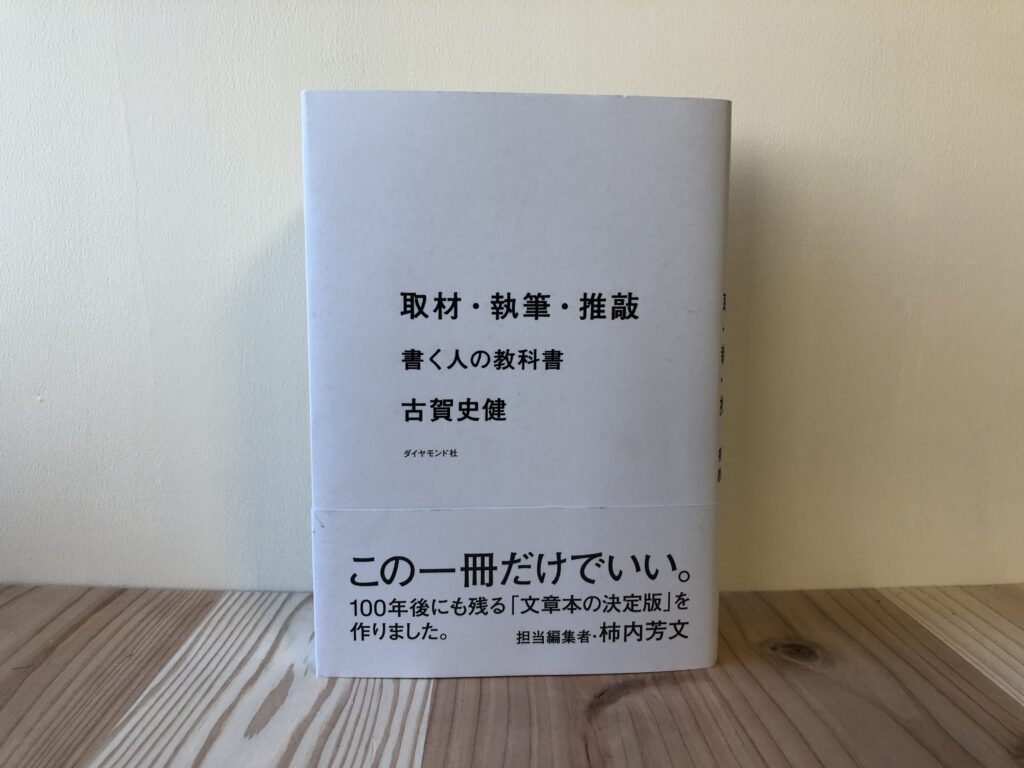2月23日の朝、ニュース番組でピンクリボンポスターの騒動を知った。
いくつかの問題が絡み合ったままで議論され、意見が交わされ、どこかで聞いたことのある結論にしか到達しないニュースを見て辟易した。気になったので調べていくうちに、少しずつ問題が整理され、頭も随分とクリアになった。
その過程をここに記しておく。
ピンクリボンポスター騒動
まずは、ピンクリボンポスターを巡る騒動について簡単に説明する。2月18日、あるツイートによって問題が表面化した。
主にツイッター上で上記のポスターに関する意見が交わされ、21日にはデザイン大賞を主催する団体の公式HPに謝罪文が掲載された。
それほど長くないので、以下に全文を引用する。
日本対がん協会が主管するピンクリボンデザイン大賞は、乳がんの早期発見の大切さを伝え、検診受診を呼びかけるとともに、正しい知識を習得していただき、ご自分に合った適切な行動を起こしていただくことを目的に実施しております。しかしながら、これまでの入選作品に対し、問題点を指摘する多くのご意見が寄せられております。選考の責任はわたくしども協会にあり、お気持ちを傷つけてしまった患者さんやご家族のみなさまにお詫びを申し上げます。また、偏った価値観に基づいて作品が選ばれているとのご批判もいただきました。ご意見を真摯に受け止め、よりよい啓発活動のあり方を探ってまいります。
公益財団法人 日本対がん協会
「ピンクリボンデザイン大賞について」(2022年2月21日)|ピンクリボンフェスティバル
22日以降は各テレビ局やウェブメディアにも取り上げられ、ツイッター上の反応と同様に否定的な意見が多かったように思う。肯定的な意見は少なく、中には、肯定か否定かといった二者択一ではなく、”思慮深い情報発信が大切である”といった教訓めいたことを書く記事もあった。ツイッターで起こったいわゆる炎上の一つであり、よくあることだとして片付ける人もいたかも知れない。
どの見方も理解はできるし、その通りだと思う意見もある一方で、どれも局所的か一面的、もしくは問題の表面をなぞっているだけのように感じた。仮によくあることなのだとすれば、なぜ頻繁に起こってしまうのか。それが分からなければ、また似たようなボヤ騒ぎがあり、時間とともに鎮火するのを繰り返す。実際、2月18日に始まった騒動も、2月末になればほとんど聞かなくなっていた。

時間が解決したのかと言えばそうではない。単に関心が薄れ、忘れられ、次に同じことが起こっても前回の経験が生かされないまま、またもや忘れられていく。その繰り返しである。よくある話であればなおさら、関心の薄れは加速する。
私たちが日々暮らし、学び、仕事をする中で、ボヤ騒ぎの野次馬でいるよりも優先すべきことはいくらでもある。ニュース一つにどれだけの時間をとったとしても、それがよくある話であれば尚のこと、新しい発見はほとんどない。また、いつもの日常が始まる。
果たして本当にそうだろうか?
看過できないことと看過してはならないこと
ピンクリボンポスター騒動についてのニュースはそこまで多くない。2週間弱しか話題になっていないので無理もない。しかし、一通り調べ終えてもなんだか煮え切らない。
なぜか? それは、僕にとって看過できない問題が含まれていて、かつ、看過してはならないと思ったからだ。
一つはポスターを作った人と大賞に選んだ人の問題で、これは控えめに言っても腹が立つ。もう一つはデザインという、業界なのか言葉なのかは一旦置いておくとして、とにかく”デザイン”を取り巻く現状に横たわる根深い問題であり、これは僕に限らず、看過してはならないことである。

(ほどけなくはない)絡み合った複数の問題
もう少し問題を細分化してみたい。まずはじめに、このポスターの目的は「啓発」である。近ごろ乳がん検診を受けていない人に対して、受診を促すことがこのポスターの役割だ。
啓発は、商品やサービスを知ってもらって買ってもらうための広告でもなければ、企業や政治家が信頼を得るための活動であるPRとも違う。宣伝や広報でもないのだろうが、それらの違いや共通点は今、問題ではない。
少し乱暴な言い方をすれば、啓発ポスターを見た人が結果的に乳がん検診を受けたとなれば、そのポスターは目的に照らすと機能したことになる。だからこそ、ポスターには人の目を引くという使命が課されているのだ。当たり前すぎるが、この大前提は問題の根っこに関わるので、それについては後述する。
皮肉な話だが、この騒動を受けて乳がん検診に行っていなかったと気づき、受診した人もいたかも知れない。炎上商法ではないが、目的を達成すればいいのかと言えば、それは違うだろう。
輸入と翻訳によって抜け落ちていくもの
根っこにある問題を検討する前に、先ずその他の小さな事柄をざっと確認してみたい。
まず、ピンクリボンとは何か? 一言で言えば、乳がん検診の早期受診を推進すること”など”を啓発する運動のことである。”など”と書いたのは、ピンクリボンに含まれる活動は他にもあり、それらが抜け落ちているがために起こってしまった問題でもあるからだ。他の活動とは、乳がんに対する正しい知識を広げたり、乳がん患者のサポートやその家族をケアすることである。ウィキペディアの英語版には、目的の全体像がしっかりと明記されている。
もともとアメリカで始まったピンクリボン運動は、2000年代に日本でも知られるようになった。当時はマンモグラフィーが普及しておらず、触診が一般的だった。そうした事情もあり、日本では触診によるセルフチェックが未だに推進されているが、乳がんにおけるセルフチェックを推進している国は日本だけだそうだ。これ以上、大した知識を持たない僕が乳がんや検診の話をするのは憚られるが、一つだけ。「セルフチェックで見つかる乳がんの多くは良性であり、定期的な検診さえ受けていればセルフチェックは必要ない」という話を、ある医師が話しているのを聞いた。今の日本のピンクリボン運動と比べると、その乖離に驚くのは僕だけではないはずだ。
タイムラグとコンペに潜む問題
騒動のきっかけになったツイートがされたのは2022年の2月18日だった。ポスターは公募で選ばれており、ツイートした人が見かけるまでには募集から審査、結果発表、そして希望した全国の病院や自治体、企業に配られるというプロセスを経ている。
審査結果が発表されたのは2021年の10月1日。騒動が起きるまでに4ヶ月弱のタイムラグがある。結果発表のあとにどれくらいの期間を経て配布され、ツイートした人が見たポスターはいつ、どこに貼られたのかは分からない。しかし、ツイートによって問題視される以前にも人の目に触れていたのは間違いない。
それどころか、募集を締め切った2021年の6月末から発表までに5段階もの審査を経ていて、その過程では、候補となるポスターに対して乳がん当事者の意見を聴く機会もあったそうである。
ここで、ピンクリボンデザイン大賞について概要を書いておく。2005年度に始まり、2021年度で17回目を数えるコンペである。日本対がん協会が主催し、ピンクリボンフェスティバル運営委員会という組織が運営している。
17回目ともなれば、かなり古株のコンペだと言えるだろう。しかし裏を返せば、毎年のように乳がん検診の啓発という同じテーマで開催し続けてきたがゆえの問題もある。それについては後ほど。
比較的歴史のあるコンペ”だから”なのか、それとも比較的歴史のあるコンペ”にも関わらず”なのかは分からないが、毎年かなりの数の応募があり、5回の審査を経る必要があるのは理解できる。
しかし、2021年度に関しては、6人の審査員が約3ヶ月の審査期間で20,000点を超えるポスターを評価するという建付けにそもそも無理があった気がしてならない。過去の応募総数を調べた結果を下に示す。

一部、調べても分からない年もあったが、応募数は増加傾向にあると言っていいだろう。昨年から20,000件を超えており、応募数が膨大なので、まともに審査できているとは到底思えない。加えて、今回の騒動では過去の受賞作も問題になっていて、無理があったのは今に始まったことではないようだ。
朝のニュース番組でこの騒動が取り上げられたとき、コメンテーターが「コンペである必要があったのか?乳がんに関わりのあるアーティストなりに委託するという方法もあったのではないか?」と言っていた。別のネットニュースではある人が「新しさはないかもしれないけど、知名度のある人を起用したシンプルな啓発ポスターでも良かったんじゃないか?」と言っていた。
コンペという方法が悪いのではない。しかし、彼女ら/彼らが言うように、コンペである必要を欠いていたとは思う。
奇をてらうということ。デザインとはなにか?
細かい話も含めて、いくつかの問題点を挙げてきた。既にメディアで触れられ、意見が交わされているものも多い。門外漢の僕が下手なことは言えない専門的な話もあったと思う。ここからは、少しだけ、自分の経験やこれまで感じてきたことも踏まえて書いてみたい。取り上げるのは、何かを”デザインする”といったときに立ちはだかる「新規性」と「公共性」の問題である。
これまでに17年連続で開催され、毎年のように多数の応募があるピンクリボンポスターデザイン大賞。テーマ(目的と言い換えてもいいかも知れない)は毎年同じなので、アイデアや表現が出尽くしていたと考える人は多いだろうし、僕もそう思う。「出尽くしているからこそ、これまでにない新しいものをつくりたい」「それを見たい」というのが、応募者や審査員の心情だったのではないだろうか?
大いに共感する。仮に、自分が同じ条件でコンペに応募したとしたら、そうした”無意識下にある感情”に逆らうことは難しかったと思う。あるいは、問題にすら感じなかったかも知れない。
しかし、確実に意識しなければならないのは、ポスターは公的な場所に貼られ、不特定多数の人が目にするということだ。コンペの結果発表から問題が起こるまでの約半年のタイムラグが指し示すのは、ひとえに、受け取り方は人によって多様ということである。その中には乳がんの患者も含まれているのは、審査の過程で当事者へのヒアリングがあったことからも想像できる。
ポスターデザインの新規性と公共性は、もちろん互いに独立ではない。新しさも行き過ぎれば公共性を欠き、その逆もある。「両者のバランスが大事なのである」というのはもっともだが、それだと結局、どちらかへの偏りが問題視されては揺り戻され、また逆へ、と繰り返すだけな気もする。
デザインの病理
この騒動に限らず、何かが問題視されたときに、侵された側の価値観へと立ち返り、その往復を繰り返すこと自体は自然である。ただ、新規性と公共性というそもそもを疑わないままに繰り返していては、前にも上にもどこにもいかない。
この問題系を少しでも先へ進めるためには、どうしたらいいのだろうか。2つの異なる価値軸に加えて、第3の何か、オルタナティブを見つければいいのだろうか?仮にそうだとしても、容易ではないし、そもそもオルタナティブを目指す姿勢が評価されてこそのコンペなので、本来は当たり前なのかも知れない。

3つの軸を想定すれば、そこに揺り戻しはなく、常に、だれも目を向けてこなかった別の可能性を模索することになる。言い換えれば、超ハードモードだということだ。二次元と三次元の間には、単にパラメータが増えて感じる困難さ以上の、厳然とした壁がある。
「デザインは表現ではない」という言説はよく聞く。しかし、では何なのかと言えばよく分からない。世に言われるデザインについて調べ、知れば知るほどその輪郭がぼやけ、少しでも気を許せば、なんでも「デザイン」という言葉で言いくるめられてしまうような暴力性すら感じる。
オルタナティブを目指す姿勢がねじれると、表現を追い求めかねない。しかし、そもそもが極めて難しいことなのだから、ねじらなければ見つかるものも見つからない。とはいえ、やはり、表現は表現であって、デザインの目指すところではない。
ここまで書いてきた”デザイン”という言葉を巡る実態や困難、そして幻想に対して、何か答えが出したいわけではないし、あるとも思えない。ただ、”オリジナルのデザイン”というオルタナティブは架空のものだという気がしてならないのだ。デザインを取り巻く環境、特にコンペのような競争空間においては、新規性や公共性への眼差しが、デザインそのものに慢性的な問題を与えているのではないだろうか?
臨床医と病理医
話は変わって、ある人が「デザイナーは町医者のようなものだ」と言っていたことを思い出す。医者が患者の具合を聞き、適切な処置をして薬を処方するように、デザイナーがまずすべきことは、相手の話をきくことである。しかし、それができるデザイナーは極めて少ないのだという。表現を求めるデザイナーは、患者との接触を避け、こんにゃく相手に針と糸で手術の練習を繰り返す外科医のようなものだろうか。それはそれで、”神の手”のような到達点があるような気もする。いや、単に医療ドラマの見過ぎかもしれない。
話を戻すと、町医者という言葉をより正確に言い換えるとすれば、それは「臨床医」のことではないだろうか。常に現場があり、目の前には”困っている”人がいる。一方で、現場にいては見えない問題があり、それに向き合うのが「病理医」と呼ばれる人たちだ。
大げさに言えば、ライターは病理医のようなものなのかも知れない。すぐには役に立てないかもしれない。しかし、話をきくことはできる。そして、同じ悩みが二度と生まれないように働きかけることで、間接的に病を治すことに繋がるかも知れない。間接性は、ライターの本質である翻訳そのものだ。
話を単純化しないように、忘れないように、ライターとしてできることから始めたい。一つのニュースからでも、それがたとえ、あっという間に消えてしまうような、小さな出来事であったとしても。
参考
https://twitter.com/ttttmmmm16/status/1494476748645289986?s=20&t=Owiql4yNnWza2e8rrzmx6A
ピンクリボンデザイン大賞について|ピンクリボンフェスティバル
対がん協会報 第707号(2021年11月1日)
ピンクリボン|ウィキペディア
Pink ribbon|Wikipedia
J-CASTニュース(2022年2月21日)
HUFFPOST日本版(2022年2月22日)
日本テレビ系『スッキリ』(2022年2月23日)
まいどなニュース(2022年2月23日)
ABEMA TIMES(2022年2月24日)
「制作者のエゴ?」乳がん検診啓発ポスターが炎上|ABEMA
ピンクリボンポスター炎上の件|守本がレターに答えるだけのチャンネル
ピンクリボンポスター炎上について|守本悠一郎のデザイントーク
カバー写真
©Ed Uthman, 2015(Licensed under CC BY 2.0)